小児矯正
当院の小児矯正の特徴

- ベストなタイミングで始める
- メリハリをつけて
- 親御さんから子どもへの
最高のプレゼントになるように
小児矯正はいつ頃
始めるのがベスト?
子どもの治療は平均9才頃に始めると言われています。
8〜9歳ごろに矯正が必要かどうか一度来院相談して下さい。
また、骨格の左右前後のズレがある場合や、埋伏している歯の位置異常など、早期に開始した方がいいケースもたくさんあります。
保護者様が心配と思った時点で一度来院して下さい。
小児矯正のメリット
将来の抜歯の可能性を軽減
早期治療の大きなメリットのひとつは、将来的な抜歯の可能性を軽減できることです。大人の矯正治療では、おさまりきらない歯並びを治すために、やむなく抜歯を行って治療をすることがあります。
しかし、子どもの矯正治療では成長発育を利用することができるため、大人なら抜歯となるようなケースも非抜歯の可能性が上がります。
コンプレックスの改善
子どもの治療では成長をコントロールできるのが利点です。将来、極端に顎が小さい、または顎が出ているなどのコンプレックスにつながる因子を少しでも減らすことができます。
発音や鼻呼吸など、正しい口腔機能
および周囲の機能の獲得
早期治療では歯並びをよくするだけではなく、それに伴った正しい口腔機能を得ることも目標にします。
正しい嚥下(えんげ)や発音など正常な口腔機能の獲得、指しゃぶりや舌突出癖など悪習癖の除去は、大人になってからだとなかなか治りませんし、治療後の歯並びの後戻りの原因にもなります。
正しい機能がともなってこそ、正しい歯並びといえるのです。
むし歯の予防、正しい歯みがきの
仕方など、口腔衛生管理の習得
定期的に来院していただく矯正治療の特性をいかして、当クリニックではお子さんのプラークコントロールを徹底します。
自分で自分の口腔内の管理ができるようになる、これも当クリニックの考える治療目標の一つです。加えて、正しいキレイな歯並びになるということは、歯みがきもしやすくなりますし、自浄性も向上し、むし歯の予防にもつながります。
おとなの矯正治療がシンプルになり、
場合によっては不要に
子どものうちから矯正治療をすることは、おとなの歯並びをより正常な噛み合わせに近づけることにつながります。子どもの矯正治療からおとなの矯正治療に移行する場合、よりシンプルな治療になり治療期間の短縮の可能性が高まります。
場合によっては、子どもの矯正治療だけですむこともあります。
小児矯正のデメリット
- 成長に合わせて治療を行うため、通院期間が長くなることがあり、
子どものモチベーションが続かないことがある - 治療内容によっては虫歯のリスクが高まる
- 治療を受けるお子様が治療の意義を理解していないと装置を使用せず効果が出ない
- 治療を行っても大人の治療で抜歯が必要になるケースもある
時間がかからないケース
- 軽度の叢生
- 骨格的に前後左右のズレがないもの
時間がかかるケース
- 骨格的に前後左右のズレがあるもの
- 埋伏している歯がある場合
治療期間について
積極的に歯を動かす期間は2年くらいですが、歯の生え変わりが終わるまで経過観察を行ったり、また治療を再開することがあります。12歳の永久歯がはえる頃まで継続的に来院してもらうことが多いです。
矯正装置を用いて歯を動かす期間=動的治療期間はだいたい2〜3年ほどです。しかしながら、子どもの矯正治療は成長のコントロールや歯の生え変わりがあることから経過観察を行ったり、途中で治療が進められない時期があるため矯正装置を使用する期間は大人の治療よりも長くなることが多いです。
1期矯正について

使用する装置について
当院で使用する装置は30種類以上あり、9割の方がオーダーメイドのもの、1割が既製品のものを使用します。
診断時に習い事などのライフスタイルに合わせて、固定式か可撤式かなどご相談の上作成していきます。
矯正治療の流れ
初診・相談
精密検査
セファロ・(CT)・顔写真・口腔内写真
診断・治療計画の決定
早期治療
定期観察
再診断
本格治療
メインテナンス
年1回のチェック
子どもの癖が
歯並びに及ぼす影響

指しゃぶりについて
0〜2歳頃
指しゃぶりは口に入ってきたものを吸う「吸啜反射(きゅうてつはんしゃ)」や自分の身体を触って確認しようとする探索反射が原因のため、お子様の成長の一部と考えられています。
なかには全く指しゃぶりをしない子もいますが問題はありません。
またアメリカの小児科学会はおしゃぶりや指しゃぶりはSIDS(乳児突然死症候群)の予防に効果的であると発表していますので、2歳頃までは心配ありません。
2歳以降
指しゃぶりは、吸う力によって、歯並びやかみ合わせが悪くなるだけではなく、舌の位置が下に下がることによって発語にも影響をもたらします。
言葉の発達が著しい2歳頃から辞めるように勧め、3歳までに止めることをお勧めします。
口呼吸による5つの悪影響
歯並びが悪くなる
顔の成長に変化
(鼻の成長が抑制される)
むし歯や歯周病を
発症しやすくなる
口臭が強くなる
風邪をひきやすくなる
歯ぎしり
子どもの歯ぎしりは、上下の前歯が生えそろってくる生後8ヶ月頃から始まり、中学生頃まで続くこともあります。
これは次に生えてくる歯の位置を決めたり、顎の成長を促すための生理的現象ですので、必要以上に心配しなくて大丈夫です。
ですが、歯が削れてしまったり、欠けてしまったり、顎の痛みを伴う場合は治療が必要な場合もありますので、ご来院下さい。
頬杖
頬杖をつくということは、下あごに頭の重みがのしかかるということです。
わずかな力ですが、あごの骨に毎日伝わり続けることで、あごの変形や顔のずれ、歯列不正を徐々にまねく怖い癖です。
矯正治療は保険でできないの?
矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。
治療期間
マウスピース矯正の場合は比較的難易度の低い症例を扱っていることが多いため、治療期間が1年半程度で書かれていることが多いですが、一般的に非抜歯治療の場合は2年〜2年6か月、抜歯治療の場合は2年6か月〜3年と言われています。
しかしながら、治療方針や歯の動くスピードによって治療期間が異なりますので、あくまで目安として考えていただければと思います。
また、その後保定期間が最低2年はありますので通院期間は5年程度となる場合が多いです。
矯正治療中に気をつけること
検査の際に治療が必要な虫歯などがあった場合には先に治療を行います。
保険治療について
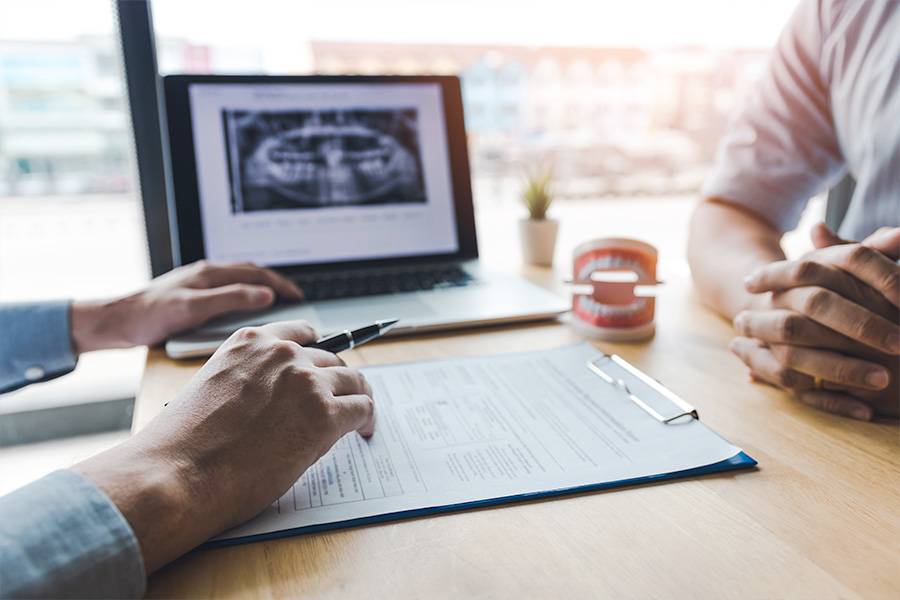
矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。
「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
(1)唇顎口蓋裂(2)ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)(3)鎖骨頭蓋骨異形成(4)トリーチャ・コリンズ症候群(5)ピエール・ロバン症候群(6)ダウン症候群(7)ラッセル・シルバー症候群(8)ターナー症候群(9)ベックウィズ・ウイーデマン症候群(10)顔面半側萎縮症(11)先天性ミオパチー(12)筋ジストロフィー
(13)脊髄性筋委縮症(14)顔面半側肥大症(15)エリス・ヴァンクレベルド症候群(16)軟骨形成不全症(17)外胚葉異形成症(18)神経線維腫(19)基底細胞母斑症候群(20)ヌーナン症候群(21)マルファン症候群(22)プラダー・ウィリー症候群(23)顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
(24)大理石骨病(25)色素失調症(26)口腔・顔面・指趾症候群(27)メビウス症候群(28)歌舞伎症候群(29)クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群(30)ウイリアムズ症候群(31)ビンダー症候群(32)スティックラー症候群(33)小舌症(34)頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)(35)骨形成不全症(36)フリーマン・シェルドン症候群(37)ルビンスタイン・ティビ症候群(38)染色体欠失症候群(39)ラーセン症候群(40)濃化異骨症(41)6歯以上の先天性部分(性)無歯症
(42)CHARGE症候群(43)マーシャル症候群(44)成長ホルモン分泌不全性低身長症(45)ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)(46)リング18症候群(47)リンパ管腫(48)全前脳胞症(49)クラインフェルター症候群(50)偽性低アルドステロン症(51)ソトス症候群(52)グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)(53)線維性骨異形成症(54)スタージ・ウェーバ症候群(55)ケルビズム(56)偽性副甲状腺機能低下症(57)Ekman-Westborg-Julin症候群(58)常染色体重複症候群(59)その他顎・口腔の先天異常
前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
なお、これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。
当院では保険適応の矯正治療は行っておりませんが、保険適応となる方には専門機関へのご紹介をいたします。
医療費控除とは
1年間で支払った医療費の総額から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象金額となります。
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円〜330万円未満 | 10% |
| 330万円〜695万円未満 | 20% |
| 695万円〜900万円未満 | 23% |
| 900万円〜1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円〜4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
この金額から申告者が支払っている税金(所得税)に応じた税率をかけた金額が還付されます。
また、医療費控除の対象額の10%が住民税から減額されます。
例1)総所得金額等300万円、医療費合計100万円、保険金なしの場合100万円ー10万円=90万円(医療費控除額)
90万円x10%=9万円(所得税還付金)
90万円x10%=9万円(住民税減税額)
合計で18万円還ってきます。
例2)総所得金額等300万円、医療費合計50万円、保険金なしの場合50万円ー10万円=40万円(医療費控除額)
40万円x10%=4万円(所得税還付金)
40万円x10%=4万円(住民税減税額)
合計で8万円還ってきます。
医療費に含まれるもの
矯正治療で支払った治療費
歯ブラシや歯磨き剤などの歯科衛生用品は対象外になります。
通院のための交通費
(バスや電車など公共交通機関やタクシー代)
自家用車のガソリン代、駐車場代は対象外です。
デンタルローンも控除の対象になりますが、手数料や利子は対象外です。
※申告の際に必要な書類や、医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは、大切に保管しておきましょう。







